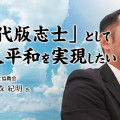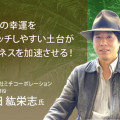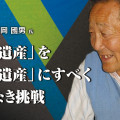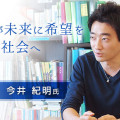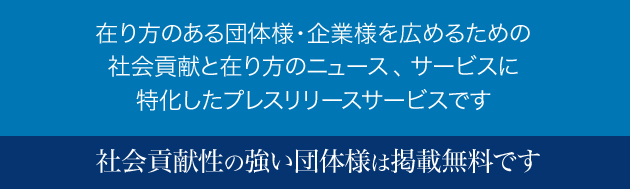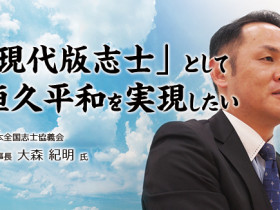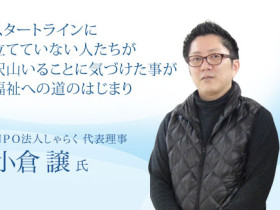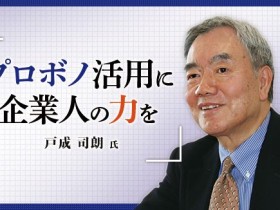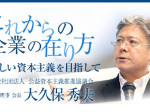吉本 誠氏【玉野を元気にするぞ】「どてきり」復活へ!玉野から世界への挑戦
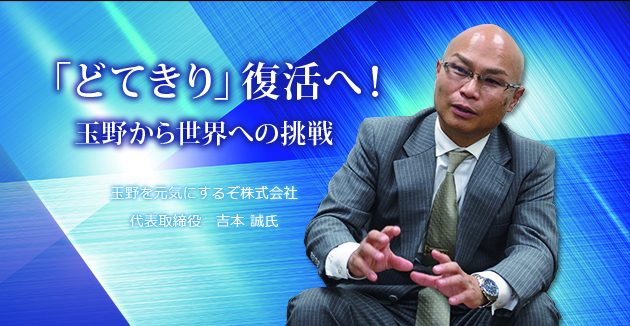
Contents
「どてきり」復活へ!玉野から世界への挑戦
岡山県玉野市。穏やかな瀬戸内海と緑あふれる山々に囲まれた、人口6万人余りの風光明美な町である。この町には、かつてこの地で多く水揚げされていた幻の蟹「どてきり」を復活させ、玉野市の特産品にしようと取り組んでいる人たちがいる。地域活性化にとどまらず、国際貢献にもつながる、濃厚で美味な蟹を使った斬新な取り組み。その名も、「玉野を元気にするぞ株式会社」の吉本 誠氏に話を聞く。<編集部より>
玉野を元気にするぞ株式会社 グループマネージャー 吉本 誠氏
地域を元気にしたいと旗揚げ
 株式会社 シーエフエス 代表取締役 藤岡俊雄(以下、藤岡): まず、現在活動をされている団体名を教えてください。
株式会社 シーエフエス 代表取締役 藤岡俊雄(以下、藤岡): まず、現在活動をされている団体名を教えてください。
玉野を元気にするぞ株式会社 グループマネージャー 吉本 誠(以下、吉本): 「玉野を元気にするぞ株式会社」です。
藤岡: もう一度、お願いできますか?
吉本: 「玉野を元気にするぞ株式会社」です。
藤岡: 「玉野」というのは地名ですよね?
吉本: はい、岡山県にある「玉野市」です。
藤岡: 吉本さんご自身は、どのようなことからこの活動を始められたのですか?
吉本: 元々、私は和食の料理人でした。日本料理店を玉野の地で始めさせていただいたのが縁で、地域活性化っていうんですかね、どんどんどんどん、この地域が衰退化していくのを目にして、これは何とかしないと今後どうにもならない、と思うようになりました。
私だけの人生だけではなくて、将来的に考えても、「町づくり」に取り組むことによって、何とかこの地に元気を出してほしいなという思いで立ち上げた会社なんです。
幻の蟹「どてきり」との出会い
藤岡: なるほど。最初に携わられたことはどのようなことでしたか?
吉本: まず、玉野商工会議所で「町づくり研究会」というものを約7年半の間に立ち上げました。
そこで「この町にしかないもの」が何かあるだろう、と調査をすることになりました。すると、「どてきり」という蟹がいたということが分かったのです。
藤岡: 「どてきり」?それは種類で言うと、どのようなものですか?
吉本: ついこの間、メディアの企画でもやっていましたが、東京湾では、この30年間で7杯しか上がっていない蟹なんです。(ワタリガニの一種で、和名はノコギリガザミ)
藤岡: 30年で、ですか?!
吉本: はい、7杯しか獲れてない。
藤岡: 獲れてない?それは、見つかっていないのですか?
吉本: はい、見つかっていません。幻の蟹です。
その蟹が元々は岡山にいて、岡山で呼ばれてる蟹の名前が「どてきり」という名前だったんです。
さらに調べていくと、文献も何にも残ってないんですけど、800年前には蟹八幡さん、「八幡」の御神体にもなっています。
藤岡: 蟹八幡? 岡山にあるんですか?
吉本: はい。日本でそこしかありません。(岡山市の「蟹八幡宮」)
武の神様ですから、強力な爪とか持っているので、多分八幡様になったんだろうと思うんですけども。
岡山を統治していた備前藩主 池田公にも、備前焼で「どてきり」をモチーフにした「香ろう」を2体献上されているんです。
藤岡: 香ろう?あの香りのする?
吉本: はい。蟹の「どてきり」の形をした香ろうで、それを献上されていたと。
私たちが「その蟹を復活させるよ」という活動をしたことにより、研究家の人たちも「あ、この蟹をモチーフにしていたんだな」ということが分かったそうです。
文献は残ってないのですが、そのような形で非常に昔から親しまれていた蟹なんです。
ところが、日本の高度成長期に干潟がどんどん埋まっていった影響で、見ることができなくなったと言われています。
「何とか、この蟹にスポットを当てて復活させて、ここ玉野の地に来ればあの蟹が食べられる、どんな店でも食べられるよっていう風にしよう!」と思い、現在のように活動を始めたんです。
「絶対あきらめない」と強く誓う
 藤岡: なるほど。では次に、現在はどんな活動をどのようにされているのか教えてください。
藤岡: なるほど。では次に、現在はどんな活動をどのようにされているのか教えてください。
吉本: はい。その蟹の復活のために、まず、岡山理科大学の山本俊政 准教授に会いに行きました。
私一人ではできませんから、やっぱり「学」の部分でサポートしてくれる先生がどうしても必要でした。
山本先生に「これに協力してください」とお願いすると、山本先生が「1つの約束を守るんだったら協力する。その約束というのは“絶対あきらめないこと”」と言われて、「絶対あきらめませんよ。先生、大丈夫です」という約束からスタートした訳です。
山本先生は非常に有名な先生ですので、復活劇を始めて半年ぐらい経った時には、もうテレビ局の特別番組を組まれましてね、1時間番組です。
その時に山本先生からの提案で、「タイに行けば非常に出回っているから、調査しに行こう」ということで、タイに養殖家もいるし、行ってみましょうと、テレビ局と一緒に行ったんですね。
その時はいろいろあったんですが、何とかその養殖をしてるところまで奇跡的にたどり着くことができました。
そこで教えていただいた稚ガ二をですね、ミャンマーとかバングラデシュからタイに入れて。すぐ大きくなりますから、それを大きくしてタイや台北に売ったりしてたんです、その養殖家の彼が。
それを見て「日本人にもできるでしょ!」と簡単に思ったものですから、これもまた調査に入りました。
やはり、安く仕入れて、日本で一次産業(原材料・食糧など最も基礎的な生産物の生産にかかわる産業。農・林・水産業など)の町づくりとして、一次産業を興していかないといけない。
やはりその意味で「玉野産」というものは必要でしたから、その養殖技術も確立していきながら、アジアのあちこちに行きました。
最終的にはバングラデシュに行き、6年間調査をしました。
現地で起業をして、現在はバングラデシュで蟹の養殖と、それからソフトシェル(ワタリガニ系の、脱皮して間もない甲羅が柔らかい蟹の総称)の生産を今スタートしたばかりです。
世界と玉野をつなぐ「どてきり」
 藤岡: ということは、今はバングラデシュで蟹の養殖をして、それをアジアに売っていらっしゃるのですか?
藤岡: ということは、今はバングラデシュで蟹の養殖をして、それをアジアに売っていらっしゃるのですか?
吉本: 今からです!
藤岡: 今から?
吉本: そう、今からスタートです。
ソフトシェルのほうは、残念ながら日本はあまり食べる習慣がないので、アメリカ向けに売るようにはなっています。
しかし、実はこれが「ソフトシェルクラブ生産事業準備調査」として、国際協力機構(JICA)による第8回「協力準備調査(BOPビジネス連携促進)」に採択されていますので、アメリカで売ったらあまり良くないものですから、何とか日本で売ることができるように、まさに今からです。
藤岡: それを地元では、「地方創生」という形でやっておられるわけですよね。
吉本: そうです。
藤岡: その関連性を教えていただけますか。
吉本: まず、例えばソフトシェルをボイルして、蟹の身だけにしたものと、それからソフトシェル。脱皮したばっかりのものと、それから、生のまま冷凍したもの、ボイルして冷凍したものと、それとスープですね、蟹のスープ。この5つのアイテムを国内に輸入してですね、まずは自社でちゃんとモデルを作らないといけません。
ですから、玉野市に当社が持っていたレストランを改築して、地産地消市場と、それから蟹の専門ラーメン店と、蟹を使った専門のレストランと、それから今まで和食のお店をやってきていますから、日本料理のお店。この4つを1つの複合施設として、これも中心市街地活性化基本計画に基いて、経済産業省からご支援をいただきながら改装して、2016年3月1日にオープン予定です。
そこを拠点に、しっかり情報発信をしていきながら、その次のステップは今も並行してやっているんですけど、「どてきり塾」というのを開催しています。対象は地域のお店屋さんですね。ソフトシェルだったらお好み焼きの中に入れても食べられますから、全部食べられるので、お好み焼き屋さんだとか、うどん屋さんにも使っていただいて、天ぷらにしても非常においしいです。
藤岡: 脱皮をしたての蟹のことを「ソフトシェル」と言うのですか?
吉本: そうです。蟹の天ぷらがあり、全部食べられるんです。ですから、うどん屋さんなどにぜひ出してもらおうということで、現在、塾を開いています。これまでに3回やり、これからは「地方、玉野市に来たら、あそこのうどん屋さんに行けば食べられるよ」とか「お好み焼き屋さんに行ったら食べられるよ」とか、中華料理店に行っても食べられますし、どのような形でも対応できる、そういった形にしていこうと思います。
藤岡: 地元で生産されたものを地元で消費する、地産地消にはなるのですか?
吉本: 地産地消ではありません。そこはバングラデシュからです。
これまで海の近くで土を掘り、水槽を作って養殖ができるような実験を少ししてきて、養殖技術はもう確立できているのです。
ただし、一次産業としては採算が合わないんです。土地が高いので。
土地を造成するとか何とかと、非常にお金がかかりますから、ここはもう難しいなということで、5年やりましたが、現在はストップしています。
藤岡: バングラデシュで作って、それをこちらへ持ってくるのですか?
吉本: そうです。しかし、それだけでは地産地消になりません。要するにB級グルメというような感覚だと、全部冷凍品使ってますからね、基本的には。
そこで、私たちも「蟹を売るところをとりあえず作ろう。その次に今年は、休耕田を使って養殖をしよう」と考えた訳です。休耕田だと土地が安く済みますから。
私がバングラデシュで構築した技術と、それからカンボジアでは、山本先生がJICAプロジェクトとして、水のないところでブラックタイガーの養殖に成功してますから、この2つをミックスすれば、私たちにもできるのではないかと思っています。
藤岡: 水のないところで?海老の養殖?
吉本: そうです。好適環境水(水にわずかな電解質を加えることで、海水魚と淡水魚が同じ水槽内で生育できるという不思議な水。海水のないところでも真水を使って海水魚を育てることが可能となる)と言って、山本先生が宇宙でも魚が養殖できるという研究をされているくらい、特殊な水なんです。
鯛と金魚が一緒に泳いでるんですよ。岡山県にあります。
貧困層の労働・生活環境の改善を
 藤岡: その蟹っていうものを元に、町を復興させていこうという覚悟は理解できました。
藤岡: その蟹っていうものを元に、町を復興させていこうという覚悟は理解できました。
では、バングラデシュの方々のためには、どのようなことをしようと思っていらっしゃるのですか?
吉本: バングラデシュの方々はBOP層(年間3,000ドル未満で暮らす貧困層)と言って、非常に貧困層なんです。
私どものスタッフの仕事だと一月に4,000円ですから、今の人たちでいうと1.5倍くらいですね。6,000円くらいで生活をされてます。
私たちは高くて、倍は払ってるんです。
しかしながら、「まず、そういう人たちの生活改善をしよう」ということで、彼らに経営者になってもらおうと思っています。
この池を私たちで借りるか購入して、ソフトシェルの機材一式を全部私どもが用意して彼らに貸します。
彼らがソフトシェルを作ったら、それを私たちが買い取ります。その買い取った分から、お貸ししてるものは返していただくんですけれども、この一つの池で5家族から6家族くらいで、組合を作ってもらう。蟹を採りに行く人、魚の餌、蟹の餌の魚を採りに行く人、このソフトシェルを見る人、ということでご夫婦・ご家族で働いていただけたらなあと思っているんですね。
藤岡: つまり、職業訓練と職業支援を行って、その仕事を通じて現地の方々を支援をしていきたいということですね。
吉本: そうですね。彼らの給料も、私の計算では3倍から5倍にはなります。彼らは本当に一番の貧困層なんですね、バングラデシュの中でも。その人たちの生活が改善されてくるということになると、国が少しは変わってくるはずです。
藤岡: なるほど。
吉本: 同時に、バングラデシュは海抜ゼロメートル地帯で、土地がどんどんなくなっています。これを日本の技術で何とかできないかと。
簡単にいけばいいんですけど、いかないだろうなと思いながらも、昔はよく川が氾濫した際に消防士の方が土手に土嚢袋を積んでいたのを見ていました。あれと一緒のような形で、2tくらいの土嚢袋を入れます。バングラデシュでは重土が(多量の粘土を含んでいて、粘性が強く、耕作しにくい土壌)多いので、土嚢袋が劣化する前にマングローブ(熱帯の海岸に森林をつくる、主にヒルギ科の常緑高木の総称)が根を張ってくれると、この土地も流れなくなりますから、これが成功すると、バングラデシュの国土が守れるんです。
それから、マングローブ植林ということで、地球環境保護です。
やはりバングラデシュはすごい力を持っていますから、そういうこともCSR(企業が社会に与える影響について責任を持ち、社会の持続的発展のために貢献すべきとする考え方)活動として、もうこれはビジネスの一環としてそういう活動にも力を入れています。
ですから、もしそれが成功すれば、バングラデシュだけではなくて、アジアの各国にも「こんなやり方をしたらマングローブが守れるんだ」と気づいてほしいです。
藤岡: あれは気候とか、さまざまな条件が要るみたいですね。
吉本: 要ります。そこのものはそこじゃないとダメなんですよ。
例えば、バングラデシュだと、50km離れてる場所のマングローブを持ってきても生えません。今、目の前のそこにあるものじゃないと。
藤岡: とても難しいと聞いたことがあります。
吉本: そうですね。それとBOPの人たちが切ってしまうんです。
切るからダメなんですよ。例えば、タイの場合は強制的に政府がコントロールして、それを破ると逮捕されますから、やっぱり一番難しいのは人間のコントロールではないかなと思いますね。
「どてきりのまち玉野」を全国に発信
 藤岡: そうなんですね。では、これから、将来に向けてどのような方向性を持たれているのかを聞かせていただきたいなと思います。
藤岡: そうなんですね。では、これから、将来に向けてどのような方向性を持たれているのかを聞かせていただきたいなと思います。
吉本: はい。まずはバングラデシュでの成功ですね。
BOPビジネスとして、「彼らの生活改善を本当にやった」という実績を残さないといけないということと、ビジネスと直結したCSR活動っていうのを成功させないといけない。
これはもう初めてですから、CSR活動っていうのは、大きな企業が口で言う、ちょっと金出して「やっといてよ」というようなものではありません。ビジネスと直結したCSR活動っていうのは本当に、私たちにとって初めての試みなので、これは非常にチャレンジし甲斐があるんですけども、この2つをしっかりと構築するっていうところがまず第一です。
第二が並行してるんですけども、地域創生ですね。
玉野だけではなく、他の地域でもいいのですが、このような今まで日本人が知らなかった、知らないような蟹にスポットを当てて、その蟹で町づくりをしていく。
本当に大変だとは思いますが「一次産業の損失」っていう大きなキーワードがありますから、これも並行してやっていくと。今年は一次産業にもう一度チャレンジしますので、一次産業の損失と、蟹のレストランができますので、そこを拠点にしっかりと情報発信をしていきながら他の地域も支援できるところがあればしていく、ということですね。
実際には種子島で、昨年からお手伝いさせていただいています。種子島も、漁がなかなか獲れなくなって、観光客も屋久島には行くんですけど、種子島には来てくれない。そこで、「種子島を何とかしたい」という熱い思いから、「株式会社 島のタカラ」という町づくり会社を作られた方がおられます。
その方が「この蟹をどうしてもやりたい」ということで、お声掛けをしていただきました。この活動はボランティアでやらせていただいています。
種子島も応援していきますし、玉野にもスポットを当てて、何とかして玉野もお客さんがたくさん来るような町にしていきたいと思っています。
藤岡: キーワードは、「蟹」ですね。これから楽しみにしていますし、またご一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
吉本: よろしくお願いします。ありがとうございました。
プロフィール 吉本 誠氏
玉野を元気にするぞ株式会社 グループマネージャー
「玉野を元気にするぞ株式会社」は玉野市の地域活性化を理念に掲げ、2011年6月に設立。玉野の地域活性化を目的とする不動産売買、飲食・食品加工および卸売飲食業、ホテル・旅館業、魚類・甲殻類養殖および販売、輸出入業・海外取引とさまざまな事業に取り組む。
http://dotekiri.com/