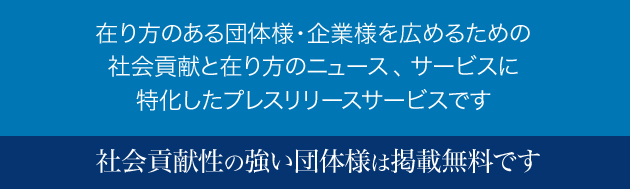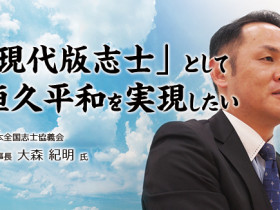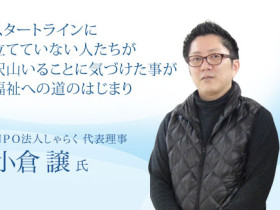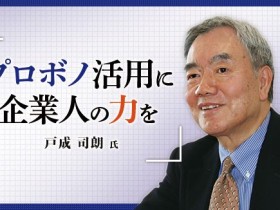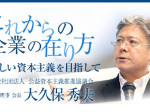西川 亮氏【Co.to.hana(コトハナ)】デザインの力で地域の課題解決を
- 2015/12/11
- 対談・インタビュー
- Co.to.hana, いしのまきカフェ, ひとしごと館, コトハナ, シンサイミライノハナ, 北加賀屋つくる不動産, 北加賀屋みんなのうえん, 西川亮

Contents
デザインの力で、社会や地域の課題解決を
大阪市住之江区北加賀屋地区。かつては造船所が進出し、工業地帯として広がりを見せたこの地区でも、現在は少子高齢化が進み、地域住民同士の交流も希薄になりつつあると言う。
その北加賀屋地区を拠点に、「デザインの力で社会問題や地域の課題を解決すること」を目的に活動を展開しているのが、デザイン事務所「Co.to.hana」(コトハナ)。
“Co”は、「協同」の意味で、さまざまな人が集まって協力すること。
“to”は、社会にメッセージを届けること。
“hana”は、みんなの想いが詰まった花を咲かせること。想いをカタチにすること。
デザインが持っている「人を感動させる力」「ムーブメントを起こす力」「人を幸せにする力」を信じ、グラフィックデザインから空間設計、コミュニティデザイン、プロジェクトの企画・運営まで多様なデザイン分野に取り組むNPO法人、「Co.to.hana」代表の西川 亮氏に話を聞く。<編集部より>
西川 亮 氏 NPO法人 Co.to.hana (コトハナ) 代表
さらにデザインが活躍できる場所を求めて
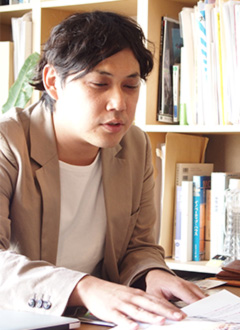 株式会社 シーエフエス 代表取締役 藤岡俊雄(以下、藤岡): この団体を立ち上げようと思われたきっかけは、どのようなことだったのですか。
株式会社 シーエフエス 代表取締役 藤岡俊雄(以下、藤岡): この団体を立ち上げようと思われたきっかけは、どのようなことだったのですか。
NPO法人 Co.to.hana (コトハナ) 代表 西川 亮(以下、西川): デザインというものは、営利目的と言いますか、「より便利なものをつくる」とか「商品を売る」ためにあり、経済と共に発展してきた歴史があります。
しかし一方で、世界中の9割の人は、デザインされたものに触れる機会がないのです。日本やアメリカで作られた、オシャレなかっこいい服なんて買うこともできない。
ある展覧会でそういうことを知りまして、その時に「世界や社会、地域課題も含め、デザインが活躍できる場がもっとあるのではないか」と感じたのです。
僕自身は「デザインを社会課題や地域課題の解決のために活かす」ことに取り組んでいきたいと思い、団体を立ち上げました。今年で5年目になります。
言葉で伝えるのが難しくても、ものや形になれば広がる
 西川: 私たちが行っていることは、具体的に3つあります。
西川: 私たちが行っていることは、具体的に3つあります。
1つは、NPOやNGO団体さんのブランディングやデザインのお手伝いです。
NPO団体は、どうしても情報発信が苦手だったり、自分たちの問題解決に取り組むことで手一杯になったりしがちです。
そこで、後回しになりがちな「伝える」という行為を、デザインの側面からサポートしています。
実際にはWEBサイトを作ったり、チラシを作ったり、空間をデザインしたりと、幅広くやっています。
2つ目は自主事業です。
まず最初に立ち上げたのは、阪神・淡路大震災の記憶と経験を後世に語り継いでいく活動「シンサイミライノハナ」です。
「シンサイミライノハナ」の展示は、阪神・淡路大震災からちょうど15年が経過した2010年から始めました。震災を知らない世代がどんどん増えていく中、「震災を経験していない世代に対し、震災から学んだ経験や教訓について、どのようにしたら興味を持ってもらえるか」と考えたのが、この「花」のオブジェでした。
メッセージカードを花びらに見立てて、1枚1枚に震災への思いやメッセージを書いていただきます。5枚組み合わせることで、1本の「シンサイミライノハナ」が咲きます。「街中やいろいろなところに花を咲かせることで、震災のことを思い出したり、考えたりする機会を作る」という取り組みです。
日本国内のみならず、インドネシアのスマトラ沖地震や東北の被災地、ニューヨークでも、計15万人以上の方々にメッセージを書いていただきました。来年(2016年)の春にはフランスでもメッセージ募集の話があるのですが、被災の経験や記憶を書いていただいています。
インドネシアで最初に活動を行った際は、宗教や文化の違いなどから、果たしてこれが受け入れられるのか心配もありましたが、実際には多くの方に参加いただくことができました。
「言葉だけで伝えようとすると難しいことも、こうしてものになった時、形になった時に広がりを見せていく」ことを改めて感じました。
これは大学卒業後に始めたもので、現在で5年目になりますが、まさにこのような活動を、いろいろな社会問題に広げて取り組んでいきたいなと思っています。
空き地活用が人々のつながりに
 西川: もう1つの自主事業が、「北加賀屋みんなのうえん」です。
西川: もう1つの自主事業が、「北加賀屋みんなのうえん」です。
これは地域の空き地を活用して畑にし、人のつながりを作るようなコミュニティの場を作っていこう、という事業です。
現在は人口減少で、都市部でも空き地がどんどん増えています。地域に住む人にとっては、防犯上も見た目にもよくありません。
空き地を活用すると言えば、どうしても駐車場になりがちですが、「どうすれば、その地域に住む人たちにとって豊かな暮らしの場にできるか」と考え、畑にしました。
「みんなのうえん」では、道の舗装や倉庫づくり・家具づくりをみんなで行い、もちろん野菜も自分たちで育てます。そこで採れた野菜を使ってベントをしたり、ケータリングで、企業様のイベントや、結婚式のお食事の提供をさせていただいたりしています。
参加メンバーは主婦が多いのですが、主婦の方が自分でカフェをしたいと思った時に、実際に店舗を構えるのは大変なので、ここでカフェ営業を1日だけやってみることもできます。他にもケータリングで腕を磨いたり、実践したりという活動の拠点になっています。
 藤岡: これは、自治体と連携しているのでしょうか。
藤岡: これは、自治体と連携しているのでしょうか。
西川: 元々は、地元の不動産会社の業務委託で始めました。現在は、参加費やケータリングの収益などで事業運営をしています。
事業自体は持続可能なモデルになってきているので、私たちがサポートし、東京都足立区でもこのような農園が生まれています。
最近では行政の方々も多く視察に来られ、余っている土地の活用について参考にしていただいています。
藤岡: 東京でも展開しているんですね。
西川: 東京都足立区の農園を運営しているのは僕たちではなく、現地の不動産会社さんにノウハウを全部お伝えして、ご自分たちでやっておられます。
世代や所属を超え、人がゆるやかにつながる場所
 藤岡: 昔で言えば町内に公民館があるような、それの発展形ですよね。それがコミュニティの場でしたから。
藤岡: 昔で言えば町内に公民館があるような、それの発展形ですよね。それがコミュニティの場でしたから。
西川: そうですね。どうしても地域の公民館とかだと、町内会に入っている方が集まる場所になっていたと思いますが、最近は若い世代だと町内会に入らない方もいらっしゃるので、「世代や町内会などの枠を超えたつながりをどう作っていくのか」を大事に考えています。
ある福祉団体さんが利用されていて、障がいを持っている子どもたちが野菜を育てるなどの活動を行っていますが、結果、その団体さんに加入する方も増えているそうです。
「農園を持っている福祉団体」というような打ち出しがされていて。僕たちにとっても農園の利用者が増えるのは嬉しいことですし、そういった相乗効果も生まれています。
農園活用で新しいご縁が生まれる
 西川: この農園の大きな特徴として、8人で1つのグループを作ることがあります。
西川: この農園の大きな特徴として、8人で1つのグループを作ることがあります。
そうすると、1人の人が水やりをするのは週に1回で済んだり、月に数回農園に来るだけでいいという状態になったりします。
通常の市民農園を自分たちで借りると、毎日のように世話をしなければいけないので、結構大変です。それに比べれば、手軽に都市部の中で、働きながらでも参加できるコミュニティになっています。
参加したい人が1人ずつ集まっていただくのですが、チームはこちらで組むので、知らない人同士がチームになります。そこでも、新しいご縁が生まれるような仕組みになっています。他にも大学のサークルや友人同士で、借りることもできます。
街づくりでキャリア教育を
 西川:そしてもう1つ、「NPO法人スマイルスタイル」と「NPO法人み・らいず」と一緒に、3法人で立ち上げた事業があります。
西川:そしてもう1つ、「NPO法人スマイルスタイル」と「NPO法人み・らいず」と一緒に、3法人で立ち上げた事業があります。
これは、宮城県石巻市で、東日本大震災の1年後にスタートした取り組みです。
石巻市では企業が被災して、高校生の就職先が地元からなくなってしまい、高校を卒業したら地元を離れざるを得ないという状況がありました。
その中で、どうしたら高校生も街づくりに関わることができるか、あるいは高校生自身も「地域のことを知らずに去っていくのではなく、地域のことを知り、自分で考え、形にしていける場を作ろう」ということで、地元の企業と一緒にキャリア教育として始めました。
企業からの寄付金を予算として、地元の高校生が40名ほど集まり、ゼロからカフェを作りました。商品開発をしたり、カフェ運営をしたりする中で、自分たちで考えて商品やお店を作るという経験が、学校生活では得られない貴重なものとして高校生の成長につながっています。
藤岡: この取り組みは、非常に有名になっていますよね。
西川: そうですね。
地域の困りごと解決から、仲間づくり、生きがいづくりを
藤岡: 最後に、今後の目標や課題に感じていることなどを教えてください。
 西川: 新たに、大阪市浪速区で始めている事業があります。それが「ひとしごと館」です。
西川: 新たに、大阪市浪速区で始めている事業があります。それが「ひとしごと館」です。
浪速区は生活保護受給者やひとり親家庭、外国人の方、単身世帯が多く、地縁のコミュニティが築きにくい地域です。
そこで生まれている課題は、生活の中でのちょっとした困りごとです。
例えば高齢者の方が「自宅の電球を取り換えたいけれど、自分ではできない」とか、外国人の子どもが、言語の壁によって地域になじめないでいるとか、さまざまな課題があります。
そういった地域の困りごとを、同じ地域内の元気な人や、技能を持った人たちが解決する仕組みを作っていこうというものです。
「ひとしごと館」は「地域住民のとくいが集まる施設」として、企業勤めをリタイアされ、豊富な知識や知恵を持っている方に関わっていただいたり、主婦の方が空き時間を使って関わっていただいたりという形を考えています。
必要な誰かに自分の特技を提供する、それが完全なるボランティアではなく、ちょっとした「ひとしごと」ということです。
「ひとしごと館」では「ひとしごと」する登録メンバーをカードで一覧できるようにし、利用者がパッと見た時に、この人は何が「とくい」なのかを分かりやすくする工夫も行います。
「ひとしごと」はアルバイトまではいきませんが、たとえ少しでもちゃんとお金を得てもらい、収入を得ながら、その活動を通して仲間づくりをして、助け合い、生きがいを作っていくような形を生み出していこう。この「ひとしごと」を地域に広めていくことで、人々が輝ける社会を実現していきたい。
そのような思いで、2016年2月1日から「ひとしごと館」をオープンしてやっていきます。
 藤岡: 「ひとしごと館」のモデルは、ご自身で考えられたのですか。
藤岡: 「ひとしごと館」のモデルは、ご自身で考えられたのですか。
西川: 有償ボランティアは、世の中に既にあったものですが、実際に機能させるのは簡単ではない状況の中で、以前から問題意識は持っていました。
身近なところで言うと、僕の父親も退職してからアルバイトをしていますが、それまでにやってきた仕事と全く関係のない仕事をしています。「これまでの経験を生かしながら地域の活動に関わり、それを仕事にもできたら、世の中が変わるのではないか」という思いがあります。
これは全国的な課題でもあるとは思うので、まずは浪速区から始め、全国に広げていきたいと思っています。
プロフィール 西川 亮 氏
 NPO法人 Co.to.hana (コトハナ) 代表 / デザイナー
NPO法人 Co.to.hana (コトハナ) 代表 / デザイナー
1986年大阪生まれ。神戸芸術工科大学を卒業後、NPO法人 Co.to.hanaを設立。
社会の問題や地域の課題に対して、デザインが持つ「人に感動を与える力」「ムーブメントを起こす力」「人を幸せにする力」で課題解決をめざし活動。各分野にとらわれず、問題の本質をつかみ、「ヒト」「コト」「モノ」のコミュニーケーションをデザインしています。issue + designプロジェクト最優秀賞受賞。 http://cotohana.jp/