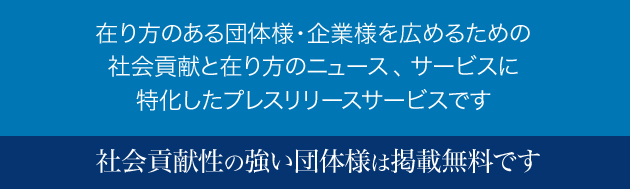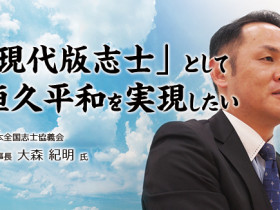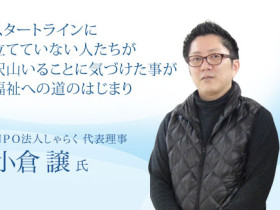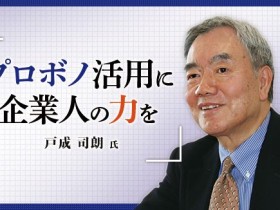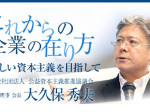栃原晋太郎氏【栃木DARC】新しい人生の一歩をここから

Contents
新しい人生の一歩をここから
薬物依存症者の回復に向けたリハビリ施設として知られる「DARC(ダルク)」。「DARC」とは「Drug Addiction Rehabilitation Center」の略で、薬物依存症者が共同生活を送りながら、社会復帰をめざす。
国内に数あるDARCの中で、今回スポットを当てるのは、栃木県内で5つの施設を運営する栃木DARC。自身も薬物依存の経験があり、現在は職員として薬物依存症者の社会復帰を支援する、アウトリーチ部長 兼 1st Stage Center施設長の栃原晋太郎氏をゲストに迎える。
栃原氏は、栃木DARCに入寮したばかりのメンバーの回復支援を行うと共に、刑務所や保護観察所などでの回復プログラム実施、学校などでの講演を通した薬物問題に関する啓発活動も精力的に行っている。栃木DARCには薬物依存症者の社会復帰を段階的にサポートするために3つの事業体があり、これまで100名以上の方々がプログラム終了後、社会再参加を果たした。<編集部より>
栃原晋太郎氏 NPO法人 栃木DARC アウトリーチ部長 兼 1st Stage Center施設長
薬物依存症の当事者として
 有限会社アップライジング 代表取締役 齋藤幸一(以下、齋藤): 栃原さんは、一般社団法人 栃木県若年者支援機構の代表理事 中野謙作さんをよくご存じだとお聞きしました。中野さんも素晴らしい活動をされていますよね。
有限会社アップライジング 代表取締役 齋藤幸一(以下、齋藤): 栃原さんは、一般社団法人 栃木県若年者支援機構の代表理事 中野謙作さんをよくご存じだとお聞きしました。中野さんも素晴らしい活動をされていますよね。
NPO法人 栃木DARC アウトリーチ部長 兼 1st Stage Center施設長 栃原晋太郎(以下、栃原): そうですね。行政では届かないようなところを、NPOのような枠組みで支援していくと言う点で、中野さんは私のモデルとなる方です。
私は過去に8年間覚せい剤を使用していました。薬物依存症の当事者です。
最初は良いことがあるから薬物を使い続けていたのですが、実は良いことなんて何もありません。妻とも離婚することになりました。他にも借金などいろいろな問題の末に、栃木DARCにたどり着いたのです。
当事者として回復プログラムを約3年経験した後、職員として栃木DARCに関わらせていただくようになりました。12年が経ちます。
齋藤: 薬物使用を止めてから、12年と言うことですか?
栃原: はい、薬物を使わなくなって12年経ちました。
中野さんとは、私が栃木DARC職員になった頃、宇都宮でお会いしました。自分が正しいと思っていることを、純粋な気持ちからボランティアで行っている方がいるんだなと感心したものです。
それまで私を取り巻く人間関係は、同じように薬物を扱う人が多く、中野さんに初めて会った時は、「こんなふうにきれいに生きてもいいんだな」と衝撃を受けました。中野さんは私の活動における血潮と言いましょうか、今後も何かある毎に、中野さんに相談をしながら活動を続けていくことになると思います。
齋藤: 当社でも中野さんの紹介で、少し訳ありの方が2名働いています。本当に一所懸命、皆と一緒に仲良く働いてくれています。彼らの可能性を、私たち雇用側が入口で勝手に止めているだけだなと感じました。
今後も、中野さんにはたくさんの方を紹介していただくでしょう。来るもの拒まずじゃないですけど、「職場体験させてほしい」と言われれば、「いつでも来てください」と言えるような気持ちで事業を行っています。
栃原: 取材の話をいただいてから、齋藤さんのFacebookを拝見し、お会いするのを本当に楽しみにしていました。
栃木DARCは、代表理事の栗坪千明や職員を含めて全員、薬物依存の経験があります。ですから、外部の方が関わりづらいと感じられるのは当然のことと思います。初対面で来ていただけることは普段なかなかないことですので、正直驚きました。
「薬物依存症という病いに回復はある」という思い
齋藤: 今回、Facebookのページで、栃木DARCさんが薬物回復プログラムの教科書を作るために、クラウドファンディング(製品・サービスの開発、アイデア実現などの目的のために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募ること)を行うと拝見したことがきっかけです。
まず、すごいことをやろうとしている人がいるなと感心しました。応援させてもらおうと思い、その後、ぜひ取材させてもらいたいと思うようになったのです。
物事を自分でやろうとする人たちは、世の中少ないのではないかと思っています。チャレンジしても、だめな可能性もある。やらないで、後々、やっておけばよかったと感じる人たちが多い中、自分たちでチャレンジすることって、すごくパワーがあると感じるんです。
チャレンジして、もしダメだったとしても、どこがダメだったのか考えて再チャレンジする。「違う方法があるかもしれない」と考えながら生きていくことのほうが、余程楽しいなって思うんですよね。
そのようなパワーがある人たちに会いに行くことが私は大好きなので、今回取材に来ました。
栃原: ありがとうございます。
私は、栃木県大田原市の黒羽刑務所で約10年前から、栃木県さくら市の喜連川社会復帰促進センターでは設立当初の8年前から、受刑者教育にも携わらせてもらっています。
日本では、薬物問題は「病気ではなく犯罪」という認識がまだ強くあります。
薬物使用者は刑務所に行くべきで、その後出所したとしても、回復や地域に根付くための支援やお金は、行政が出しづらい分野なんですよね。
確かに、薬物使用者は身勝手な理由で薬物を使用し始めてはいますが、使い続けると、本人が止めたくても止められなくなるというのが、薬物依存症という病なのです。ですから、適切な治療とサポーターがいれば回復することも可能です。
そのことを理解してくださる方々が少しずつ増えてきて、私たちの活動も次第に広がってきています。
刑務所内の教育だけでなく、出所した人たちが行く保護観察所でのプログラムや、栃木県宇都宮市の県立岡本台病院の医療観察棟の病院の中でもプログラムを行っています。そこから、「テキストを作ろう」というアイデアが出てきました。
覚せい剤使用で初めて逮捕された人は、約2か月は拘留されますが、基本的に執行猶予が付いて釈放されます。
しかしその結果、再犯率は60%にもなります。また逮捕され、2度目は刑務所に長く行くことになるのです。
この制度は何だかおかしいですよね。そこで立ち上がってくれたのが、栃木県でした。
栃木県では6年程前から全国で初めて、初犯の執行猶予者を集めてプログラム提供をスタートさせました。
初犯の執行猶予者、2回逮捕され刑務所へ行った人、刑務所から出所した人、医療が必要で病院にいる人。栃木県では、多くの方にプログラムが提供できるようになりました。
また、当事者には家族がいます。栃木県では、家族に対する支援や、家族に対して薬物依存症を知ってもらうような教室、家族会も充実しています。
統一された薬物回復プログラムの構築を
 栃原: 私たちが回復プログラムに関わるようになってから、10年が経ちます。
栃原: 私たちが回復プログラムに関わるようになってから、10年が経ちます。
この間、地域ごとにプログラムや社会支援も増えてきていますが、各々がつながっていないと言う問題があります。
それはなぜかと言うと、例えばある刑務所では、回復のため一番効果がありそうなプログラムを持ってきて、受刑者に提供する。ある保護観察所では、回数制限があるため、少ないプログラムを持ってきて、職員も勉強して、一緒に取り組む。そのような、各所個別の形で運営しているからなのです。
初犯の執行猶予者。逮捕され刑務所へ行った人。出所して監察所に来た人。
さまざまなケースがある中で、似たようなプログラムをまた最初から取り組む形になる場合も多く、時間が無駄になっていると考えられます。
そこで、私たちは考えました。
テキストが一緒であれば、例えば、「この人は初犯執行猶予者向けプログラムが、1クール終わりました。アンケートから見て、理解度は相当高いところまで来ています」と情報交換がなされる。その結果、薬物についての振り返りよりも、出所してからの社会再参加や、どのようなところに就職するか、家族との関係をどうするかという方向へのプログラムを考えたり、支援が手厚くできるはずなんです。
また、関係機関の職員さんは刑務所でも監察所でも、約2年で転勤になる中で、個々が専門書で勉強し、回復プログラム運営に取り組まれています。
そうして構築されたものが、人事異動により、また一からスタートになるのはもったいないことですよね。さまざまな行政の垣根もあるので難しいとは思いますが。
栃木DARCは、現在栃木県内でやっているどのプログラムにも、一応携わっています。
ですから、その経験を活かし、まず私たち主導でどこでも納得できるようなテキストを作ります。次に、それをさまざまな場所で使ってもらう。その結果、効果があることを確認してもらえれば、進度や評価が一律に付けやすくもなるでしょう。
また、同じテキストを使い、ファシリテーター(中立な立場を守り、参加者の心の動きや状況を見ながら、プログラムを進行していく人)についても、同じ養成テキストを使えたとしたら、援助者もより多く参加できると思います。
将来的に、もっとたくさんの場所で、薬物依存症者・薬物乱用者の回復プログラムができるようになることが必要なので。
そのために、統一されたテキストと統一された援助者側の理解をもって。プログラムが成される必要があると思っています。
齋藤: 素晴らしいですね。栃木県で結果が出ているとなれば、まず近県から「教えを乞いたい」、「テキストはどのようなものを使っていますか?」となりますよね。そうやって全国に広がっていく。
これから先、薬物依存者数が、日本だけではなく世界中でも減っていき、万一罪を犯した方も社会復帰しやすいような環境になっていけたら、ものすごく良い世の中になりますね。
栃原: ここ毎年、日本では11,000人が覚せい剤使用で逮捕されています。そのうち、再犯者が約65%です。暴力団の構成員がその半分を占めてはいますが、薬物乱用防止の講演活動をどんなに中学校や高等学校で行っても、毎年11,000人が捕まるというのは変わらないのです。
「刑の一部執行猶予」制度に対応した仕組みづくりが急務
 栃原: このタイミングで、私たちが動き始めた理由ががもう1つあります。
栃原: このタイミングで、私たちが動き始めた理由ががもう1つあります。
2016年6月1日から、薬物事犯者を主な対象者として、刑務所で長期服役させるのではなく、社会の中で再犯防止を図る「刑の一部執行猶予」制度が施行されました。
先ほどお話ししたように、初犯で逮捕された場合、執行猶予が付き、釈放され。2回逮捕されると、2回目は刑務所に行くことになる。
そうすると、刑期が約3年になるのですが、2年は刑務所で、残り1年は社会の中で、更生・回復のプログラムを受けるという形での判決が2016年6月から実際に出るのです。要するに、今まで刑務所にいた人たちが、毎年7,000人規模で、社会の中に出てくるのです。
しかし、これはただの枠組みで、「刑務所にいてもお金がかかるし、仕方ないから」という感じです。出所して、保護者がしっかり彼らを監督し、「早めに社会復帰を」と言っても、現在はその人たちが受けられるプログラムがないのです。
この人たちに向けたプログラムを作らないと、さらに再犯率が上がると考えられます。
齋藤: そうですね。誘惑もいっぱいあるだろうし。挫折してしまう可能性もありますよね。
栃原: 今年の6月から、この判決が出た場合、最短で約1年後から出所してくる人たちがいます。
このタイミングで、その人たちに向けたプログラムを作って、残りの1年でやれるところを全部共有し、対応する機関を増やした上で、彼らの受け入れを行わないといけません。
その対応をしないと、制度は作ったものの、誰もプログラムを受けられません、と言うことになりかねないのです。やるなら、今このタイミングがリミットかなと思っています。
齋藤: いささか危なっかしいですね。出所してきたはいいけれど、後は個人ででやってくれと言われても。そのためのマニュアルだったり、テキストが必要ですね。テキストはある程度、できておられるのですか?
栃原: 栃木ダルクでは、10回版としてT-DARPPというテキストをすでに使っているので、これをベースにデザイン変更などをして、今回24回版を作ろうとしています。
今回の対象者は、執行猶予3年のうち、2年を刑務所で1年を社会に出て過ごすことになります。かつ、最後の1年はそこのみ問題なく過ごせば、罪がなかったことになるのではなく、最大5年経過を見ます、という制度なのです。
と言うことは、最大5年間のプログラムを受け続けなくてはなりません。
そのため、1クール10回、月に1回のプログラムを組み立てると、60回は行わなければなりません。10回版のテキストでは、繰り返しが多くなり過ぎてしまうのです。
また、薬物問題の回復テキストとして、10回でまとめようとすると、1回あたりの分量がどうしても多くなってしまいます。
それを24回まで増やせると、1回当たり内容の濃いものが提供できるので、24回版は適切だと考えています。
こちらが今、栃木DARCで使っている10回版のテキストです。
これに付随してファシリテーター、司会進行者用のテキストを別に作っています。
齋藤: すごいですね。やはり、すべてに「仮名」がふってあるんですね。
栃原: そうですね。最終学歴が中学卒の方も多いので、「ふりがな」がない時点で、読む気を失くしてしまうことがあります。
「私の人生も財産、人の役に立つのかもしれない」の気づき
齋藤: 薬物を使用すると疲れが取れるなどと聞きますが、そんなこと本当にあるんですか?
栃原: 現実問題として、薬物、特に覚せい剤を使用すると、私の体験談からになりますが、使っても良いことしかなかったですね。2~3日睡眠を取らなくてもずっと仕事ができますし、怖いものや不安がなくなって、男らしくいられるという感じで、けんかをしても痛くもなかったです。
最初は良いことばかりのように思いますが、使用し続けていくと、自分では気付かないうちに、人生の中心が、少しずつ薬物にシフトしていって、気付いた時には、止めたくても止められないという状況になりました。
止められないから、だんだん薬の量が増えていき、お金もたくさんかかるので、借金までする。薬物使用を隠すために、嘘ばかりつくようになり、冷静でいたら論破されるから短気にもなっていく。もう、自分がなりたくなかった自分になっていくと言うのか、笑うこともなくなってしまいました。
齋藤: なるほど。しかし、今現在はもう薬物使用を止めていますよね。
やはり、そのきっかけというのは、さまざまな方々たちとの出会いですか?
栃原: そうですね。出会いも大きいとは思います。
今ではどこに行く時でも、「栃木DARCの栃原です、過去に薬物使用をしていました」と皆さんに言えます。でも薬物を使用していた時は、もちろん違法ですから、悪いことをしている自覚もありますし、DARCにたどり着いてリハビリが始まった時も、自分の人生は、どうしようもなく、「屑」みたいなものだと思っていました。
しかし、薬を止めてから2年ぐらい経った頃、初めて教育参加させてもらった黒羽刑務所で、「私は薬物使用を最初は楽しんでいたけれど、止まらなくなって、大好きだった妻や子供とも離ればなれになり、今はDARCに入寮しています。この先、絶対に薬物を使用しないという自信もないし、最悪の人生です」と話をしました。
その時、受刑者もその場にいた刑務官の先生たちもすごくうなずいてくれて「分かります」と。共感してくれる人がいたんです。
そこで、「私の人生も、人の役に立つのかもしれない。ちゃんと財産なんだなと感じて、DARCの職員としてやっていこう。薬物使用を止めるのもありかな」って思えるようになりました。
齋藤: その体験は、社会に相当必要とされますよね。やっぱり皆、隠しますもんね。
面接を受けに来た人から、「すみません。私は昔、覚せい剤をやっていました。DARCで更生して、現在はやっていないです」と言われても、なかなか採用と言う会社は少ないと思います。仮に隠して仕事に就いたとしても、罪悪感が出てしまいますよね。
栃原: まさにその通りです。初期施設は那須の山奥ですが、最終ステージは宇都宮で、社会復帰に取り組みます。
ここの人たちは、プログラムを受けたら、ハローワークなどに行って、職探しをするんですけど。栃木ダルクとしては、出来るだけ正直に面接の時に話をするよう話しています。
例えば、「私は3年前まで黒羽刑務所にいました。その後も薬物問題を抱えて、栃木DARCに入寮し、今はプログラムを終えて卒業ということになったので働きたいです。もう一度、私にそのチャンスをいただけませんか」という面接をしようと言っています。
やはり薬物依存症の時、僕らは嘘ばかりついていたし、やましいことばかり抱えていて、結果として、自分が苦しくなったという経緯があります。
僕は薬を止めて12年経ちますが、今でもたまに使いたくなります。それで使うかどうかは別ですが。
彼らもこの先、DARCを卒業して、仕事を始めても、人間関係でつまずくことや、思い通りにいかないことなんて、いくらでもあると思います。
その度、薬物依存症だと正直に言えていたら、会社や仲間に相談したり、定時で仕事を終わらせてもらうような相談も出来るかもしれません。
しかし、もう1つ実情をお話しすると、面接時に「そういうことがあるかもしれないので、相談させてほしい」と言うと、面接等で落ちてしまうのです。私たち施設職員が同行したとしても、落ちる人は、就職試験に30社とか落ちるんです。あまりにも採用されないから、1回心が折れてしまう人もいますが、正直でい続けて、最後に雇ってくれた会社は、本人たちの中で大事になるんですよね。
それもあって、「簡単に雇用されない」というプロセスも、私は大切だと思っています。
薬物依存について正直に話すかどうか迷う人もいますが、基本的には、皆、社会再参加したいんだなと感じます。最近はあまり景気が良くないこともあり、苦戦を強いられている面もありますが、皆がんばっています。
ダルクの中には、薬物依存症以外に、発達障がいや統合失調症などの重複障がいのあるメンバーもいます。栃木県若年者支援機構さんで、支援制度を利用させてもらう方もいます。そのようなメンバーは、働くこと自体はできるのですが、新しい職場で人間関係を築くのにすごく時間がかかったり、エネルギーが必要だったりします。ですから、理解ある方々が増えてくださるというのは、私たち職員にとっても心強いですね。
齋藤: 当社でも、さまざまな方が働いています。
現在宇都宮店では、直接雇用の障がい者さんが2名。施設外就労で、就労継続支援A型事業の方が7~8名、就労継続支援B型事業の方が2名います。
また、発展途上国支援も考え、外国人の方もどんどん雇用しています。技能実習生が3名、労働ビザで来ている人が1名、日本語学校に通っているベトナム人も4名います。
高齢者雇用で、78歳、77歳、71歳の方もおられますし、児童養護施設からの雇用もしています。児童養護施設を卒業されて就職された方には寮に入っていただき、一所懸命仕事をしていただいています。また、「潰瘍性大腸炎」と言う、厚生労働省より特定疾患に指定されている難病の方も働いています。
そんな一風変わった人がたくさんいる会社ですから、もし、栃木ダルクさんから働いてみたいという方がいれば、ぜひともアップライジングに来てもらいたいですね。(インタビュー後、1名の方が入社。2016年7月現在在籍中)
栃原: ありがとうございます。理解者が増えることは、私たちにとって本当に宝です。
薬は止めたけど、ずっと生活保護制度下での生活を強いられると、また人生に面白味を感じなくなって、薬物に戻ってしまうこともあります。そのような意味からも、DARC卒業生にはやはり社会の中で働いて、社会再参加ができる、社会で活躍することも当然できる、ということを知ってもらいたいのです。
そのためには、やはり理解者が必要ですし、協力してくださる雇用先も、もっと増やしていけるように活動していきたいと思います。
齋藤: 今回の取材をWEBサイトに掲載しますので、見てくれた方で「うちも協力しよう」と感じてくださる会社も増えるといいですね。私は必ず増えると思います。
この取材が、本当に良かったものだと思っていただけるように。栃木を変えて、日本を変えて、世界を変えるものと私は思っていますので、ぜひ今後とも、いろいろ協力させていただければと思います。本日はありがとうございました。
栃原: ありがとうございました。

プロフィール 栃原晋太郎氏
 NPO法人 栃木DARC アウトリーチ部長 兼 1st Stage Center施設長
NPO法人 栃木DARC アウトリーチ部長 兼 1st Stage Center施設長
1974年1月6日、東京都小平市生まれ。東京都立清瀬高校から日本大学工学部に進学。薬物依存症当事者。
現在は自身の経験を活かして、DARC利用者やその家族に対する支援を行う一方、刑務所や保護観察所、精神科病院などでの回復プログラム実施に携わる。学校や一般向けの講演などを通し、薬物問題に関する啓発活動も精力的に行っている。
http://www.t-darc.com/
インタビューア 齋藤幸一 氏
 有限会社アップライジング 代表取締役
有限会社アップライジング 代表取締役
1975年11月14日、栃木県宇都宮市生まれ。作新学院高校英進部から法政大学経営学部へ進学。高校、大学時代にはボクシング部のキャプテンを務めた。
プロボクサーとなるが24歳で引退後、平成18年、有限会社アップライジングを設立。
現在、代表取締役社長に就任し、世界中のタイヤ関係者が修行に来る中古タイヤ屋さんをめざして、新たな世界を極めようと日々奮闘している。